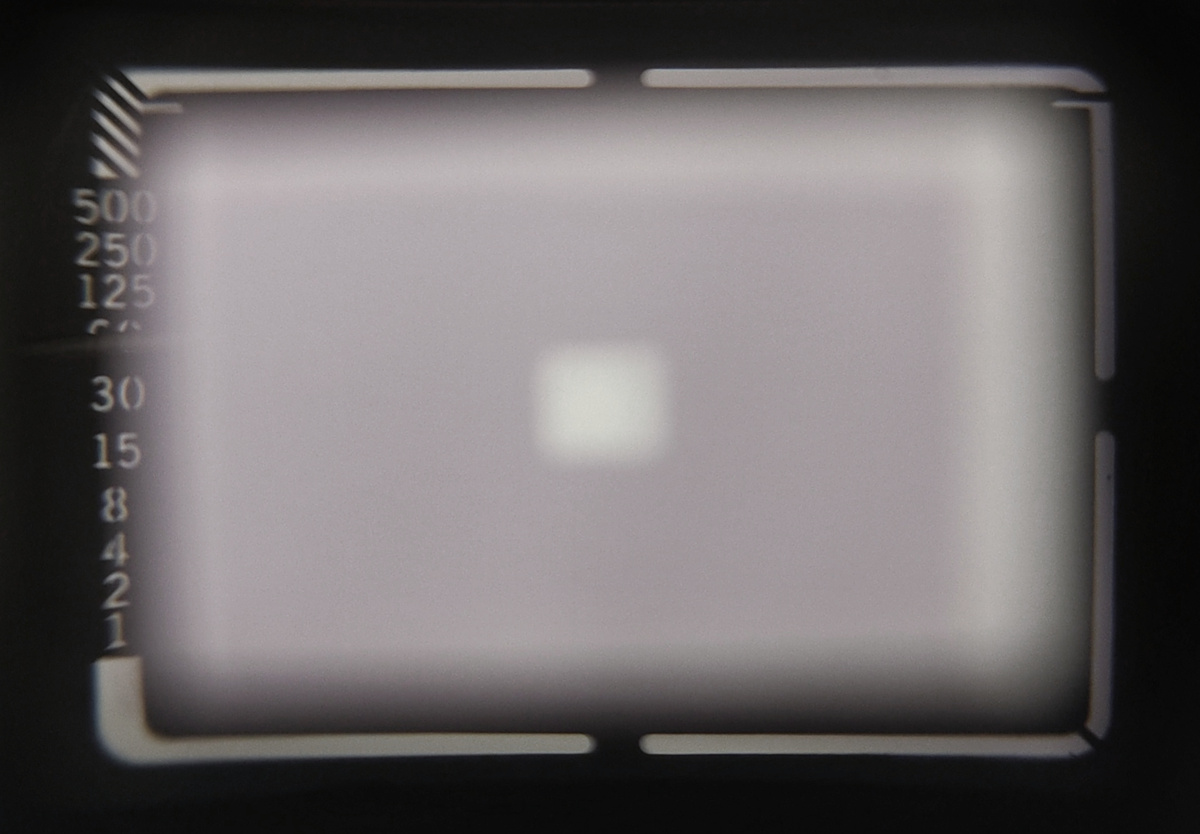カプセル型レンジファインダーカメラ オリンパスXA
2015年8月
オリンパスXA は、一見ただのコンパクトカメラのように見えて、実は光学式の距離計(レンジファインダー)によりピント合わせを行うことが出来る、ちょっとこだわりのあるカメラだ。
距離計はもともと、戦艦の砲撃などの際に敵までの距離を正確に計測するために開発された。これがカメラのピント合わせに本格的に用いられるようになったのは、1932年に高級カメラの両巨頭「ライカ」「コンタックス」に距離計が備えられてからであり、以降、距離計は本格的なカメラの条件の1つになった。しかしその後、撮影レンズがフィルム上に結ぶであろう像そのものを直接確認できる一眼レフカメラが登場し、1960年頃には急速に距離計カメラの座を奪っていく。その後も距離計は中級カメラ(キヤノネットやオリンパス35, ミノルタハイマチックなど)に用いられ続けるが、1977年に登場したオートフォーカスカメラ「ジャスピンコニカ(C35AF)」の登場により、いよいよその息の根を止められてしまい、超高級機ライカや一部の中判カメラ、復刻版的な側面を持つカメラを除くと世の中から消えてしまう。そのような中で1979年に登場した、いわば最後の「普及版」距離計連動式カメラがこのオリンパスXAである。
普及版といってもオリンパスXAは、一連の「カプセルカメラ」XAシリーズの中では高級機である。その後、XA2を始めとしたいくつかのモデルが発売されるが、それらは目測式や固定焦点式となり、距離計は省略されている。もっとも、そのために価格は大幅に引き下げられ、親しみやすいカメラとなったことで商業的に成功したのはXA以外のモデルであった。
それではなぜXAは距離計を装備したのだろうか。これには、オリンパスにおいてOM-1やペンFシリーズなど数々の名機を生み出した、故・米谷美久氏を抜きに語ることは出来ない。
米谷氏の回想 によると、XAシリーズ全体のコンセプトは「ケースレスカメラ」である。実際に、バリアをスライドするとレンズやファインダが完全に隠れ、そのまま遠慮せずに携帯できるスムーズな形状は、プラスティックの特性を存分に活かした、今となっては当たり前のようだが当時は極めて斬新な優れたものであった。しかし米谷氏は、カメラマニアであっても不満の出ない、本格的な作品作りに耐えられるカメラとしての機能を落とすことに抵抗があったのではないか。XAシリーズはフルサイズフォーマットのカメラとしてはそもそも極めて小さいカメラであり、そこに距離計や露出系指針を入れるのは並大抵のことではなかったと思われる。もちろんXAの開発には多くのエンジニアが関わっており、数々の技術的課題はチームによって解決されたが、やはりその困難な課題に立ち向かうのにはカリスマ・米谷氏の指導力あってのことだったと言われる。
XA は距離計を備えるだけでなく、絞り値を自由に選択できる絞り優先AEが備わっていること、ファインダ内にはアナログ指針により露出計が求めたシャッター速度が明確に表示されることなども特徴として挙げられる。小型であるが、操作部材は適切に大きくされており、操作がしにくいということはない。それに対してXA2はゾーンフォーカス式のカメラであるが、バリアを閉じると距離設定がパンフォーカス撮影のための中間位置に戻るようになっており、ミスを未然に防ぐようになっている点が大変優れている。XAシリーズは一見するとどれも同じような形状に見えて、実はレンズ部分のバリアの膨らみが、XAではトラック型(直線と円の組み合わせ)になっているのに対し、XA2では楕円形に、またXA1では円形に変更され、さらに両肩にも斜めに傾きが付けられており、全体にやさしい表情に変化している。主要ユーザの性別や好みに合わせて変更したとのことで、XA2では4色のカラーバリエーション展開もなされたりと、カメラ界に多くのインパクトを与えたカメラである。特にXA2はカメラとして初めて通産省グッドデザイン大賞を受賞した。
XA1 は XA2 からさらに簡略化を推し進めたカメラである。露出計はセレン式となり、電池が不要となった。ただし露出制御は割に高度で、明るさに応じて絞りの大きさが決まるだけでなく、シャッター速度も2段階に変化する。また XA1 では固定焦点式となり、ピント合わせが不可能となった。しかしその結果、いよいよ操作を要する部分がなくなり、文字通り、カバーを開いたらシャッターボタンを押すだけになった。操作のしようがないのだから、迷いがない。AFカメラのようなタイムラグもないため、極めてシャッターチャンスに強いカメラになった。
これら3機種はフィルム給送や裏蓋周りなど、共通の部分も多いが、ピント合わせの方法や露出制御方式、さらにレンズの明るさも全て異なる。また、前述のようにデザイン面での差別化が図られており、コスト面でもXAとXA2の前面の文字 "OLYMPUS" は凹んだところに白色のペイントが入れられているのに対し、XA1 ではシルク印刷となっており、ボディ上面の機種名も前面に移されている。
解説動画
VIDEO
専用フラッシュ
XAシリーズには共通に装着できるフラッシュが用意されており、装着するとカメラとほぼ一体化する。これは後の
コンタックスT などにも影響を与えており、ピッカリコニカ(C35EF, 1975年)以降、フラッシュ撮影が広く一般化したことと無縁ではないと思われる。
XAシリーズには、単3乾電池を1本のみ装着する写真の A11のほか、電池を2本装着し光量の大きいA16も用意されていた。XAでは、絞りレバーを最上段の Flash ポジションへ動かすとフラッシュの透明部分(レディランプ)がポップアップし、フラッシュに電源が入る。レディランプを押し込むとフラッシュの電源が切れて、ボディ側では絞りレバーが F2.8 のポジションに戻るようになっている。
オリンパスXAは多くのオリジナルな発想が詰まったカメラであるが、この開発に影響を与えたと言われるカメラの1つに
ローライ35 があると言われる。当時は小型カメラとしてはハーフ判カメラが流行しており、オリンパスは「ペン」シリーズによりその市場を席巻していた。そこに、ハーフ判カメラと同等もしくはそれ以上に小さいサイズでフルサイズ判の写真が撮影できるローライ35(1967年)が登場し、世界的に話題となる。XAの登場よりも10年以上先行しており、XAの開発の直接的な動機になったとは言えないが、その大きさの設定などに影響を与えた可能性はある。沈胴式に対し、専用のレンズ設計によりレンズを固定したままで薄型化した上、カプセル化を実現したところに、名設計者ハインツ・ヴァースケに対する米谷氏の意地がうかがえる。
XA と XA2 の相違点と共通点
これまでに述べたように、距離計連動・絞り優先AE機であるXAに対し、XA2はゾーンフォーカス・プログラムAEを採用している。その他にも細かな違いとして、上の写真のようにXAには1.5段の逆光補正が備わるのに対しXA2では省略されている。セットした時にカメラの転倒を防ぐ足を兼ね、解除し忘れにくい形状のセルフタイマー機能も良いアイディアである。CHECK はバッテリーチェックポジションであり、合わせると(電池があると)ブザーが鳴る。
ファインダの機能にも大きな違いがある。XAはボディ前面の絞りレバーで設定した絞り値に対し、自動的に決定されるシャッター速度がメーター指針により表示される。これにより、選択した絞り値では手ぶれの恐れがある場合や、シャッター最高速でも露出オーバーになる場合を判断できる。この大きさのボディにアナログ式(電流形式)メーターを内蔵していることに驚く。もちろん、中央部には羇旅系の二重像がある。XA2には左側のシャッター速度表示はなく、ブライトフレームの枠だけとなる。
フィルム室の内部は、レンズ設計が異なることによりレンズの見え方が異なるほかは、大きな違いが見られない。機能が大きく異なるカメラであるが、なるだけ共通化してコストを削減する工夫が見て取れる。
背面も同様であり、見た限り、裏蓋や巻き戻しクランク(右のXA2の色が異なるのは経年劣化によるものと思われる)、シャッターボタンなど多くの部分が共通のように見える。